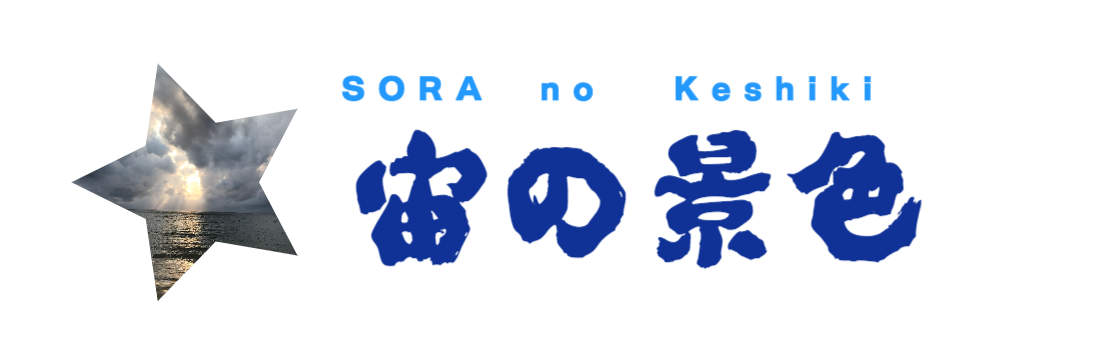2025.11.18


気象庁富山地方気象台で実習
今年も気象庁富山地方気象台で2年生の実習を行い、気象庁業務や防災気象情報、屋上や露場で見学し勉強させてもらいました。気象台のみなさま、ありがとうございました。今年の2年生からは理学部理学科自然環境科学プログラムとなりました。今までと同じように幅広く自然環境科学を学び、様々な自然環境分野の研究に取り組んでいくことと思いますが、どの分野でも気象庁データは重要かと思います。しっかり学び、気象災害や防災・減災について正しい知識と行動力を得て社会に旅立って欲しいと願います。
2025.11.13




博物館展示論の実習
博物館展示論の理学系の授業の一環として、今年も富山市科学博物館で実習を行いました。普段は来館者の立場で訪れる博物館ですが、今回は学芸員の目線での実習を行いました。実際に展示の前で展示解説を行いましたが、どうだったでしょうか? はじめての経験だったと思いますが、このような経験から様々なことを学び取ってくれたのではないでしょうか。学芸員や関係各位のみなさま、ご協力ありがとうございました。学生のみなさま、また、富山市科学博物館に遊びに来てください。
2025.11.08


第37回富山県高等学校文化祭自然科学部研究発表会
今年も富山大学理学部で第37回富山県高等学校文化祭の自然科学部研究発表会が開催されました。急に秋の気配を感じられるようになったというか、このまま冬になるのではと言う感じですが、今年も多くの高校生が集ました。口頭発表7件、ポスター発表7件と、年々、発表件数が少なくなっているような気もしますが、活発な発表会が出来たのではないかと思います。このような研究発表の経験を活かし、今後の勉強や研究などに役だってくれることを願っています。みなさま、おつかれさまでした。
2025.11.05


最後?の清水港袖師第一埠頭へ
JAMSTECの海洋地球観測船「みらい」を利用した「海洋上の大気エアロゾルの光学的特性」の船舶観測は、MR25-06の航海で全て終了となりました。私たちは、1999年のMR99-K01の航海以来、四半世紀以上の「みらい」の海洋観測に携わってきました。この場を借りて、関係各位に御礼申し上げたいと思いますし、本当にこのような機会を長年提供して頂き感謝いたします。コロナ以降は清水港が大半でしたが、母港の「むつ市関根浜」は何度も通いましたので、大変懐かしく思います。この船は、原子力船「むつ」から始まり、長い間、いろいろな意味で日本のサイエンスを見守ってきたかと思いますが、私と同い年でもあり、最後の観測機器の撤収作業は寂しさしかありませんでした。本当にありがとうございました。
2025.10.13 - 2025.10.15




24rd AeroCom / 13th AeroSat workshop
今年もAeroCom meeting で研究発表してきました。今回の開催地、当初はアメリカ開催だったのですが、諸般の事情?により、2年連続フランス開催になりました。と言うことで、今年はパリ郊外のパリ・サクレー大学のパスカル研究所でした。何も考えずに会場がある研究所に向かいましたが、大学は広大な高台にあったため、駅やホテルからは登山?かと思うような急勾配を20分ぐらい登らなければいけなかったので大変でした。特に、ホテルへは森(山)の中を歩くので、迷子になるかと思うぐらいでしたが、学生が通学で使っていたので、毎日大変だなぁと感じました。登るのはつらかったですが、森林浴に少し癒やされました。今年も楽しい時間を過ごすことが出来て楽しかったです。
2025.10.10 - 2025.10.16




フランスに行って来ました
目覚めると広大な雪原が
AeroCom meetingのため、HND-CDG便に搭乗です。いつになったら戦争が終わるのか、未だに行きのヨーロッパ便は北極回りのロングフライト。ただ不謹慎かも知れませんが、オーロラなど普段見られない景色を見ることが出来ます。今回も目覚めたらあたり一面、真っ白。寝ぼけているのかなぁと思いながらも冷静に考えると、写真のようにグリーンランド上空でした。見てて飽きない癒やされる光景でした。会議の前にリールで仕事だったので、いつものようにブリュッセル空港でもよかったのですが、今回は久しぶりのシャルル・ド・ゴール空港。TGVでリールへ行き、いつものレストランでランチ。来週は、パリ郊外で会議です。今回もいろいろな刺激と宿題を持って帰るのでしょうね。
2025.09.29




旭川東高等学校に行って来ました
学びのフローラ 〜第15弾〜 season 10
高大連携事業(出張模擬授業)のため、北海道旭川市にある北海道立旭川東高等学校に行って来ました。今回は北海道と久しぶりの遠征でしたが、どさん子の私としては北海道に帰ると落ち着きます。久しぶりの旭川でしたが、旭川駅とその周辺が綺麗になっていたと外国人の多さにびっくり。今回、多くの生徒さんに参加して頂き、本当にありがとうございました。いろいろなお話しが出来て、楽しい時間を過ごすことが出来ました。北海道の生徒は元気です! みなさんにサイエンスの楽しさが伝わり、それぞれの進路を決めたり将来の夢を考えるのに役に経ってくれればと願っています。今回は、お声をかけて頂きありがとうございました。
2025.09.19






大阪・関西万博2025 イタリア館のイベントへ
Conoscere per proteggere – Knowledge as the key to protection
2025年9月19日、大阪・関西万博2025のイタリア館で、イタリア国立研究評議会(CNR)の地球システム科学・環境技術部門(DSSTTA)が主催したイベント「Conoscere per proteggere – Knowledge as the key to protection(守るために知る)」に参加・発表してきました。生物多様性、海洋、極域、気候変動、自然災害という5つの環境テーマについて、日伊の専門家が集まり知見を共有しました。私とCNRのCairoさんとで「気候変動」の前半を担当し、30年以上の日伊はもちろん国際的な太陽放射観測ネットワークについて、「記憶 としての知識」をキーワードに、環境変化への理解と、地球規模の課題に対するレジリエンス の向上に向けた科学的対話を展開してきました。朝から夕方までイタリア館に缶詰だったので、博覧会の様子は良くわかりませんでしたが、とにかく、地下鉄から始まり博覧会場内の人の多さにびっくりでした。このようなイベントで、我々の研究を紹介する機会を頂き関係各位に感謝しております。みなさま、今後ともよろしくお願いします。
2025.04.18 - 2025.04.20










立山・室堂平積雪調査2025
今年も立山積雪調査2025を無事に終えることが出来ました。今年は、私も島田先生も授業など業務が忙しく、立山黒部アルペンルートの全線開通日(4月15日)から開始することが出来ませんでした。が、、、全線開通日から3日目の朝までは降雪のため、富山側から登ることが出来なかったので、結果的にさらに積雪も増えよかったかと思っています。今年の立山積雪調査の積雪深は676cm(2025.04.19現在)でした。ちなみに、昨年の雪の大谷は14mでしたが、今年は16mだそうです。コロナ後は少しずつ参加者が増え、今年は総勢32名で無事に掘ることが出来ました(富山大学理学部・都市デザイン学部、早稲田大学、九州大学、北海道立総合研究機構、富山県立大学など)。この積雪調査は、立山黒部アルペンルート(立山黒部貫光)、立山室堂山荘など多くの山岳関係者のご協力により継続することが出来ています。この場をお借りしてお礼を申し上げます。
今年の冬は比較的寒かったので積雪も例年並みに戻り、中層から下層はしまった綺麗な積雪層でした。黄砂が飛来していたり、予想以上に気温も高かったたり、1日目の夜に降雨があったりで、調査中でも積雪層に変化が見られました。全線開通日から運休となった降雪は、一番上の層の50cmぐらい、真っ白な積雪層でした。帰る3日後には半分ぐらいになっていましたが。その下の幅広い汚れ層は、日本全国に飛来した黄砂でした。いくつか氷板も見られましたが、予想の6mを超え、今年は掘るのが大変でした。調査には関係ないですが、18日夜に長野県北部でおこった震度5弱の地震とその余震は、富山市内はほとんど揺れを感じなかったと聞きましたが、立山の山の上では少し大きな揺れを感じました。立山で地震を経験したのは初めてだったので、少し驚きました。今年は新しい取り組みとして、積雪中のマイクロプラスティックなどの調査も行い、さらに様々な角度から立山の環境、地球の環境を分析・解析し、研究を進めていきたいと思っています。参加して頂いたみなさま、お疲れ様でした。
積雪調査動画紹介:理学部YouTubeチャンネル
積雪調査動画紹介:アルスの礎2019年8月1日放送分
積雪調査紹介:未来を拓く:おもしろい授業(富山大学)
過去の立山積雪調査の様子
立山黒部アルペンルート(立山黒部貫光)
立山室堂山荘
2025.04.07

新年度はじまる
理学部理学科となり2年目を迎えた新年度。どんな新入生が入ってきたのでしょうか。新2年生は、正式にプログラム配属され、新たなスタートを踏み出すことでしょう。行動制限がなくなった現在、学生にはもっともっとアクティブに活動し、この学生時代にいろいろ吸収して欲しいと思います。今年度はどんな年になるのでしょうか。今年度も世界中を飛び回り、ワクワクしながら研究を楽しみたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
2025.02.28


再び珠洲へ
珠洲のスカイラジオメーター観測再開
年末にご機嫌ななめだったスカイラジオの修理が終わり、再び珠洲に観測機器機を設置に行って来ました。晴れるはずだったのに、写真の通りの曇天。少し設置に苦労しましたが、何とか再開出来ました。珠洲サイトの近くの災害廃材置き場の横を帰り通り、あまりの光景に言葉も出ませんでした。。。
2025.02.09


第12回北信越地区自然科学部研究発表会 in 富山
今年度は、各県で開催された高文祭自然科学部発表会で県代表となった北信越(富山・石川・長野・新潟)の高校生の代表が富山に集まりました。北陸の大雪の影響で、残念ながら新潟県代表の4校のうち3校が参加することが出来ませんでした。昨年の北信越大会(金沢開催)も能登地震の影響で開催することが出来ず、自然災害に翻弄されていますが、自然科学を研究している生徒には、身をもって自然を学んで欲しいと思います。今年も様々なサイエンスの分野の研究発表があり、審査委員長として楽しい時間を過ごすことが出来ました。賞を取った生徒も取れなかった生徒も、さらにサイエンスに興味を持って、理学系の大学に進学し、サイエンスを楽しんでくれることを期待しています。
2025.02.07


降り続く雪
今年は雪が少ないと思っていた人も多かったのではないでしょうか。あの暑かった夏はどこへ?地球温暖化だからこその大雪と言っても良いのかも知れません。冬の日本海が暖かく、そこへ冷たい空気が流れれば雪になる。雑務に追われ富山大学の屋上の観測機器を忘れていましたが、大雪の中、自ら除雪しながら何とか動いていました。屋上は70cmを超えていました。
2025.01.31


理学部後援会報「りっか」のメイキング
2025.01.30


神楽坂との別れ
長〜年続いた東京理科大学理学部物理学科から「地球物理学・大気物理学」の研究室がなくなり、数年は観測を維持してきたのですが、そろそろ限界となりなりました。研究室の歴史からすると30余年の観測期間は短いかも知れませんが、1990年代から始めた神楽坂の太陽放射観測は、時代の流れから終わりを告げようとしています。今日は、屋上に設置していた最後の観測機器3台を撤収しました。今はなくなりましたが、昔は屋上に気象観測用の露場もあり、そこに「落第神社」も祀られていました。東京物理学校からの伝統を引きつがれた物理学の精神もあり、進級するのが難しかった理科大ならではでしょうか。学部学生時代は、日常の気象観測や太陽放射観測のみならず、月1度の24時間特別観測など東京のど真ん中で行われた観測が懐かしく思われます。神楽坂観測は終わりますが、世界各地の観測はできる限り継続していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。
2025.01.29


追浜へ
昨年9月以来のJAMSTEC横須賀本部へ行って来ました。今回は、今年の夏のMR25-04航海のシンポジウムに参加・研究発表のため、追浜に行って来ました。アナログな昭和世代としては、やはり対面でのシンポジウムは、宿題も増えますが、仕事の効率がいいです。新しい研究の切り口も見えてきたので、あとはやるだけ。。。そろそろ退役する海洋地球観測船「みらい」での観測航海は、あと何回出来るのでしょうか。今年の観測航海もよろしくお願いします。
2025.01.09


清水港袖師第一埠頭へ
今年度の海洋地球観測船「みらい」は、MR24-07で航海が終わりかと思っていたのですが、関係各位のご厚意もあり、MR25-01, MR25-02と5月まで観測航海が出来ることになりました。様々な機会をつくって頂きありがとうございます。そこで、観測機器のメンテナンスと観測のため、清水港袖師第一埠頭に行って来ました。この時期は、毎日が鈍よりした空を眺めている日本海側から太平洋側に行くと、別世界のような感覚を覚えます。写真は、みらい船上で観測中のスカイラジオメーターと右側に地球深部探査船「ちきゅう」と奥に富士山が写っています。今年もいろいろな海域でデータが取れることを楽しみにしています。
2025.01.07




珠洲へ
珠洲のスカイラジオメーターがご機嫌ななめ・・・
あっという間の1年。地震後、順調に観測を再開出来ていたのですが、老朽化の波は珠洲にも。年末にご機嫌ななめになり、1月は天候がずっと悪い状態が続きそうなので、今日行かなければ行けなくなりそうだったので、暴風雨雪の中、珠洲に行って来ました。幸い、珠洲に滞在中は晴れ間が出て良かったのですが、やはり、観測機器は壊れていました。残念ながら一時撤収して修理です。行く途中の街並みや珠洲市の街並みは、少し更地も増えた感じですが依然として変わらず。普通の生活が何かと考えてしまいますが、最低限のライフラインの早期復興を願うばかりです。
Happy New Year !
2025.01.06 本年もよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
年末年始は、久しぶりに富山で越冬しました。昨年の能登地震は北海道で冬眠していたので実感がありませんが、あれから早1年。時が経つのがさらに早く感じる今日この頃です。地球の気候も次のフェーズにはいってしまったようで、さらに自然災害の影響を心配するところですが、ひとつひとつ課題を解決していきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。